 |
 |
 |
 |
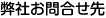 |
 |
| 有限会社 鶴仏壇工芸仏匠 広川店 |
 |
〒834-0113 福岡県八女郡広川町大字川上709-1
TEL 0943-32-5300 FAX 0943-32-5547
E-mail info@bussho.jp |
 |
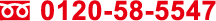 |
|
 |
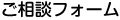 |
 |
 |
 |
| 下記フォームからお気軽にご相談下さい。 |
 |
 |
|
|
| |
 |
| |
 |
 |
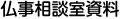 |
 |
 |
 |
 |
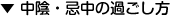
仏教では一般に四十九日の忌明け法要の日までを「中陰」と呼び、遺族はこの期間、結婚式などのお祝い事への出席は避けるようにします。
この期間に営まれる法要を「忌中法要」と言い、初七日からはじまって四十九日(七七忌/しちしちき)で忌明けとなるまで、7日おきに続きます。
現在では、途中の法要は省略されることが多いようです。
また、初七日法要もご葬儀当日に遺骨が戻ってきたところで行うことが多くなりました。
忌明け法要は原則的には、命日から49日目に行いますが、最近では、49日目の直前の日曜日などに営むことが多いようです。
日時が決まったら僧侶にお願いし、親戚や個人と縁の深かった人などに案内状を送ります。
また、法要がすんだら忌明け挨拶状を出すようにしましょう。 |
 |
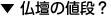
仏壇の値段は、一般の人が一目みただけでは全くわかりません。
相当値段が違う仏壇を比べてみても、どちらが高いもので、どちらが安いものなのかがわからないような場合もあります。
では、高い仏壇と安い仏壇は、いったい何が違うのでしょう?
それは、「どんな材料を使っているか」ということと、「完成までにどれだけ手間をかけているか」ということ、
この二点が仏壇の値段を決めているといってよいでしょう。
まず、材料についてですが、金仏壇と唐木仏壇では、どの材料が重要なのかが多少異なります。
金仏壇の場合、重要なのが漆と金箔です。漆は国産の漆か、外国産の漆かで品質が多少違います。
漆に似せた別の塗料を使っている場合もあります。また、金箔は純度によって値段に相当影響が出ます。
また、唐木仏壇の場合、素材の木に何を使っているかということが重要です。
唐木仏壇の美しさは、唐木と呼ばれる材木の色や木目が、いかに美しいかで決まってきます。
使われる唐木(和木の場合もあります)のほとんどは高価なものです。
特にいいものだとされるのが、黒檀、紫檀ですが、黄王檀(黄金檀)や黒柿も高級品とされます。
どの木材を使っているかで、唐木仏壇は大きく値段が変わってきます。
仏壇というものは、きわめて高度な技術によってつくられた伝統工芸品です。
仏壇をつくるには、普通、木地師、宮殿師、彫刻師、蒔絵師、金箔押師、漆塗師、錺(かざり)金具師といった職人の技術が結集されているのです。
金仏壇の場合に、漆を塗るということは、きわめて高度な技術が必要なだけでなく、気温や湿度といった天候にも塗り具合が左右されるものです。
少しでも技術が未熟だと、漆が垂れてそれが残ってしまったり、はがれたりします。高級品の場合だと、質の良い漆を何度も塗り重ねていますので、耐久力にも違いが出てきます。
金箔については、金の純度がどのくらいかということにくわえ、厚さも問題になります。
厚い方から三枚掛、ニ枚掛、一枚掛とあり、厚いもののほうが当然高くなります。
また、唐木仏壇の場合には、練り工法と呼ばれる工法があり、これによっても価格に大きく差がでてきます。
唐木仏壇は、唐木だけ無垢で作られているわけではなく、実際にはほとんどの場合、目に見えるところだけに唐木が使われています。
五〜七ミリメートルにスライスした唐木の板を芯材に張り付けているのです。これが練り工法です。
「前練り」「二方練り」「三方練り」「四方練り」とあり、どれだけ唐木を使っているかで値段も変わってくるのです。
また、唐木仏壇には、紙くらいの薄さにスライスした唐木を、木材の表面に張り付けた「ツキ板」と呼ばれる工法によるものや、
木目を単に印刷したり、木目の印刷されたビニールシートを張り付けたものなどもあり、低価格の仏壇にはこうした工法が使われていることが多いようです。
この他、組立の際に、きちんとほぞを組んで組み立てているか、あるいは接着剤だけで組み立てているかといったことや、
彫刻や蒔絵などの細工に手間をかけているかによっても値段は変わってきます。 |
 |

戒名(法名)と値段についての疑問というのは、みな口にしたくても、なかなか口にできないものです。
こうした戒名に関しての疑問について、財団法人全日本仏教会(日本のほとんどの仏教宗派が連合している組織)は、次のような決議を発表しています。
今後『戒名(法名)料』という表現・呼称は用いない。
仏教本来からの考え方からすれば、僧侶・寺院が受ける金品はすべてお布施(財施)である。
従って、戒名(法名)は売買の対象でないことを表明する。
この財団法人全日本仏教会の決議を聞くまでもなく、戒名(法名)の位が金額によって変わったり、戒名(法名)が金銭で売買されることが、いいことのはずがありません。
むしろ仏教の精神からいえば、あの世というのは、身分も位も関係ない世界であると考える方が正しいといえるでしょう。
ただ、戒名(法名)を頂いたことに対して、感謝の気持ちをもってお布施をつつむことは、悪いことではありません。
この時に、「どのくらい出せばいいのか」は宗派によっても異なるので一概には言えません。
どうしても心配ならば、知合いの方に聞くのも良い方法ですが、そうした「相場」通りにお布施を出す必要はありません。
要は、経済的に難しければ、戒名(法名)のお布施と葬儀のお布施を一つにして、「本当に少ないけれども」といって、出せる金額を出せばいいのです。
お寺によっては、一切、戒名(法名)に関してお金を受け取らないところもあるのです。
あくまでもお布施は、感謝の気持ちですので、それぞれの人が、それぞれの経済状況をふまえて、それぞれの気持ちをあらわせばいいのです。 |
|
| |
| |
 |
| |
| |
| |
| |
 |
